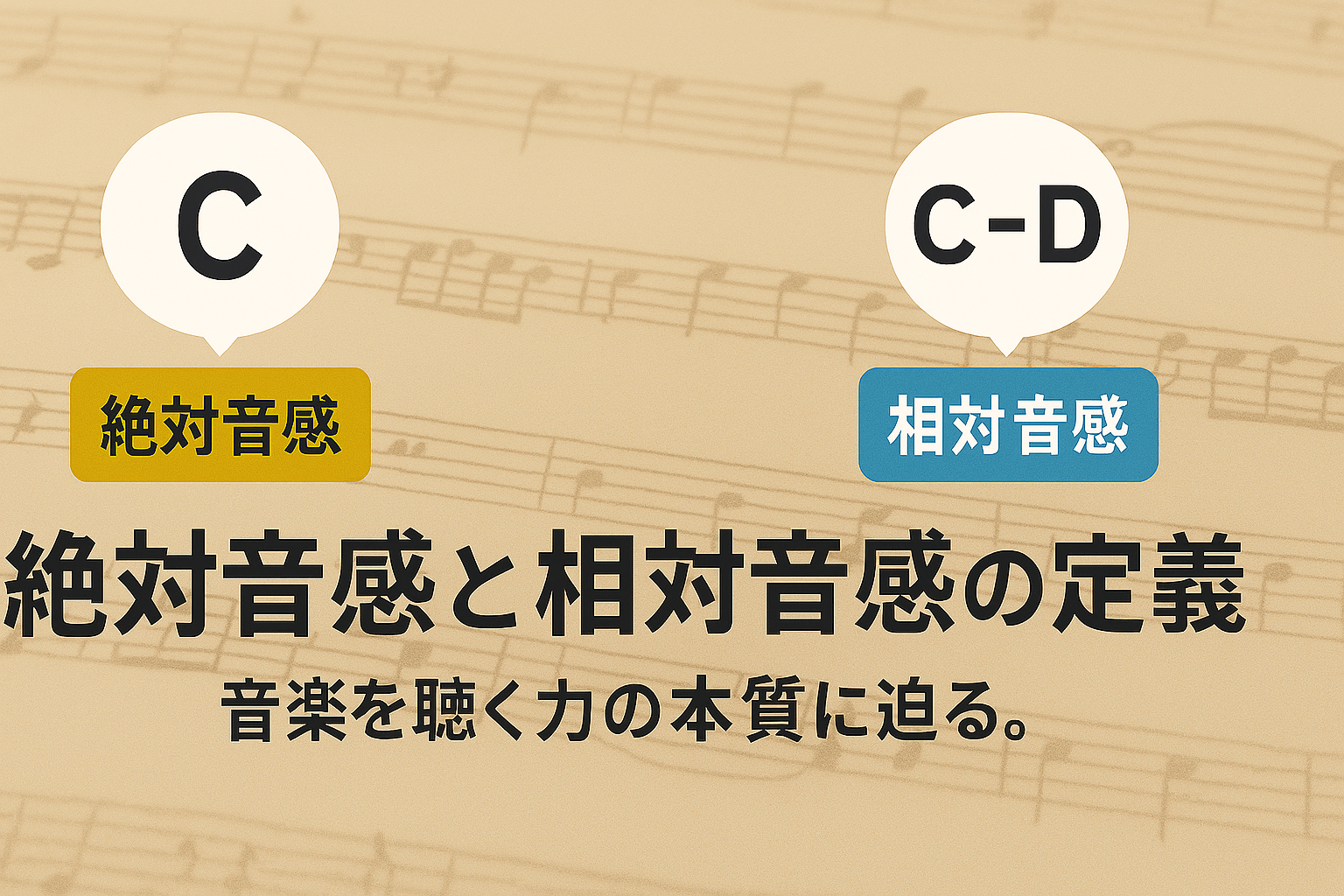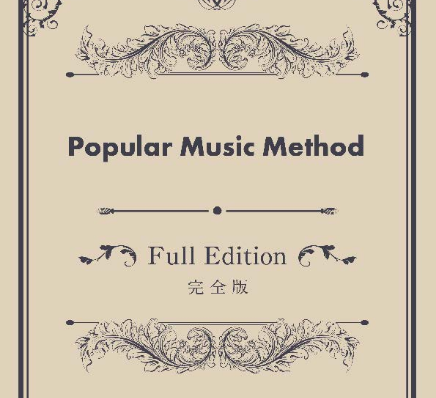はじめに|音感とは「音がわかる」ことではない?
音楽の世界では、「あの人は絶対音感があるらしい」「耳コピが得意な人は相対音感が高い」といった会話をよく耳にします。
けれど、“音感”という言葉はあまりに日常的に使われているため、その意味を科学的に正しく説明できる人は意外と少ないかもしれません。
そもそも、「絶対音感」と「相対音感」はどう違うのか?
どちらが優れているのか、音楽家にとってどちらが有用なのか?
この記事では、この2つの基本概念を学術文献に基づいて解説し、音感の正体を整理してみたいと思います。
1. 絶対音感の定義
音に“名前”がついて聞こえる能力
絶対音感(absolute pitch)とは、基準音に頼らずに単独の音の高さを即座に特定し、その名称(音名)を答えられる能力です。
たとえば、ピアノで「ラ(A4)」を1音だけ鳴らしたときに、それを聴いてすぐ「これはAだ」と判断できる人は、絶対音感を持っているといえます。
Takeuchi, A. H.(竹内明日香)&Hulse, S. H.(ハルス, S. H.)(1993)による研究では、絶対音感は“音を言語のように処理する能力”であるとされています。
つまり、音を「高い・低い」といった感覚ではなく、「これはC、これはB♭」という記号的なカテゴリーで聴き取っている状態です。
✔ ポイントまとめ:絶対音感とは
- 単音を聴いただけで音名(ドレミ、CDE)が即座にわかる
- 他の音との比較を必要としない
- 幼少期の訓練で身につくケースが多く、言語習得と類似する
2. 相対音感の定義
音の「距離感」を把握する能力
一方、相対音感(relative pitch)とは、ある基準音に対する音程(インターバル)の関係性を把握する能力です。
たとえば「ド」の音を聴いた後、次に「ミ」の音が鳴れば「長3度上がった」と判断するのが相対音感です。
このとき、重要なのは「ド」が何Hzかを知っていることではなく、2音間の相対的な“距離”を聴き取る力です。
相対音感は、アドリブ・耳コピ・移調演奏・作曲といった実践的な場面で特に重要視されます。
また、相対音感は大人からでもトレーニングによって向上できることが、多くの研究からも報告されています。
✔ ポイントまとめ:相対音感とは
- 2音以上の“音程”を正確に聴き取る能力
- 基準音を参照しながら関係性を分析
- 訓練によって後天的に獲得可能
3. 学習スタイルとの関係性
── Green(グリーン, L.)(2002)の知見より
音楽教育学者 ルーシー・グリーン(Lucy Green)は、著書 How Popular Musicians Learn(2002)において、ポピュラー音楽とクラシック音楽では音楽学習の前提が異なることを示しました。
- ポピュラー音楽の学習は、耳(リスニング)を中心とした相対音感的アプローチに依存しており、聴いて真似て弾くプロセスが中心。
- 一方で、クラシック音楽は記譜に基づいた学習(譜読み・音名理解)が基盤となっており、絶対音感が重視されやすい傾向があります。
このように、音感の種類は単なる能力の違いではなく、音楽文化や教育方法と深く結びついていることがわかります。
4. どちらが優れているか?
── 能力の比較と実用性
| 能力名 | 特徴 | 得意な場面 |
|---|---|---|
| 絶対音感 | 単音を即座に音名として認識 | 聴音、調律、固定ドの楽譜読み |
| 相対音感 | 音と音の関係性を聴き取る | 移調、耳コピ、作曲、アドリブ、実演 |
音楽家の中には絶対音感を持たないプロも多数います。
実際には、相対音感の方が実用性が高いとする意見も多く、どちらが優れているかは一概に言えません。
また、絶対音感は移調や転調に混乱を生むケース(例:固定ド vs 移動ド)も報告されており、万能な能力ではないことも重要です。
5. 結論|音感とは“構造理解”の力
音感とは、単に「音がわかる」力ではなく、音をどのように“意味づけて”理解しているかという認知の枠組みです。
- 絶対音感:音を“名前”で処理する能力(固定的・ラベリング)
- 相対音感:音を“関係性”で理解する能力(柔軟・構造的)
どちらを重視するかは、音楽のジャンル・目的・学習スタイルによって変わります。
自分の得意なスタイルを知ることで、耳のトレーニングや楽譜学習の方法にも具体的な方針が見えてくるはずです。
📚 参考文献
- Takeuchi, A. H.(竹内明日香) & Hulse, S. H.(ハルス, S. H.) (1993). Absolute pitch. Psychological Bulletin, 113(2), 345–361.
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.113.2.345 - Levitin, D. J.(レビティン, D. J.) & Rogers, S. E.(ロジャース, S. E.) (2005). Absolute pitch: perception, coding, and controversies. Trends in Cognitive Sciences, 9(1), 26–33.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15639438 - Deutsch, D.(ドイチュ, D.) (2013). The Psychology of Music (3rd ed.). Academic Press.
https://www.sciencedirect.com/book/9780123814609 - Green, L.(グリーン, L.) (2002). How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education. Ashgate / Routledge.
https://www.routledge.com/How-Popular-Musicians-Learn/Green/p/book/9781138270039